龍のエサと潟龍 〜アンガーマネジメントから生まれた我が家の文化〜
ある日、ふと立ち寄った書店で『翻訳できない世界の言葉』という本に出会いました。その中にあったのが、ドイツ語の「Drachenfutter(ドラヘンフッダー)」という言葉。直訳すると「龍のエサ」という意味ですが、実はこれ、怒らせてしまった妻や恋人の機嫌を直すために贈るプレゼントを指す言葉なんです!
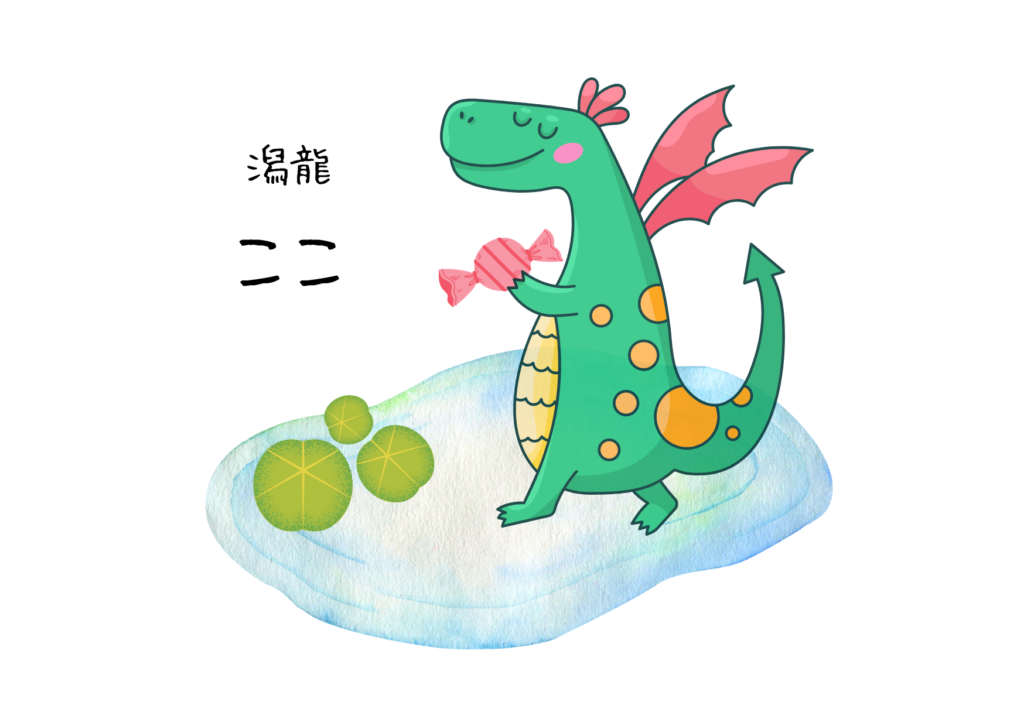
当時の私は、アンガーマネジメントの専門家として、「感情を言葉にすることの大切さ」を伝える活動をしていました。
怒りという感情は、決して悪いものではありません。適切に表現すれば、むしろ人間関係を良くするための大切な力になります。また、怒りは時に、もう必要のなくなったものを壊し、新しいものを生み出すエネルギーにもなります。
負の感情は、押し殺すものではなく、上手に活かしていくもの。
そんな考え方の中で出会ったのが、「龍のエサ」という言葉・・・。
この言葉に出会った瞬間、「なんて面白い表現なんだろう♪」と、心がふっと軽くなったのを覚えています。
家族にシェアしたら…
この「龍のエサ」という言葉の面白さを家族にもシェアしてみたところ、当時まだ小学生だった息子たちはすぐに気に入りました。
それ以来、私がイライラしていると、夫に「ねぇ、龍のエサ買ってきて!」とお願いするようになったんです(笑)。
こうして我が家では、
「龍のエサ=誰かの気持ちがざわざわしたときに、みんなで食べるスイーツ」
というユニークな文化が生まれました。
夫がコンビニスイーツや、地域の美味しいお店のスイーツを買ってきてくれて、家族みんなで囲んで食べる。
すると自然と会話が生まれ、怒りもほぐれ、気づけば笑い合っている。
そんな時間に、私は何度も救われながら、育児の日々を乗り越えてきた気がします。
もちろん注意点として、「甘いものはイライラを悪化させる可能性がある」という研究結果もあるそうです。
でも、私は思うんです。
適量を楽しみながら、家族とのつながりや心の安らぎにつながるなら、それはとても価値のある“エサ”なのではないかと。
「潟龍」の由来
私は、自分のことを「潟龍(がたりゅう)」と名乗っています。
その由来のひとつは、先ほどお話しした「龍のエサ」のエピソード。
怒りをただ押さえ込むのではなく、ユーモアと対話の力で乗り越える——そんな日々の中で、私の中に“龍”が住んでいる感覚が芽生えました。
もうひとつの理由は、私が深くお世話になっている新潟の潟(かた)たち——福島潟、鳥屋野潟、佐潟などの存在です。
四季折々の自然、美しい水辺の風景、そしてそこに生きる人々との温かなつながり。
この地で生きることへの感謝と、自然との共存を大切にしたいという思いを込めて、私は「潟龍」と名付けました。
怒りのエネルギーを破壊ではなく再生の力へ。
そして、自然と共に呼吸しながら、この土地でしなやかに、時に力強く生きていく。
そんな「潟龍」としての在り方を、これからも大切にしていきたいと思っています。
怒りは悪いものじゃない
「Drachenfutter(ドラッヘンフッター)」というドイツの文化、そして我が家で生まれた「龍のエサ」の文化。
このふたつを振り返ると、私はいつも思うのです——怒りも、ユーモアや工夫次第で、人と人とをつなぐ力になり得るのだと。
アンガーマネジメントの視点から見れば、怒りは抑え込むべき「悪い感情」ではありません。
むしろ、それを適切に表現し、活かすことで、建設的なエネルギーへと変えることができます。
我が家の「龍のエサ」も、まさにその考え方が形になったものでした。
家族の誰かが怒っていたら、「龍のエサ」の出番。
スイーツを囲んで、自然と会話が生まれ、笑顔が戻る。
その小さな時間が、家族や地域との絆を深め、心をリセットし、新たな一歩を踏み出すエネルギーになるのです。
そして今、私が手がけている物語「いにしえの物語~福島潟の名前の由来~」の中にも、登場人物・お福の怒りが描かれています。
かつての怒りを現代に生かし、その想いを地域の価値を伝える力へと昇華することができたなら——
それはきっと、幸せを広げる力になる。そう信じています。
これからも私は、怒りという感情を上手に活用しながら、家族や地域の絆を育み、笑顔を共有する文化を育てていきたいです。
